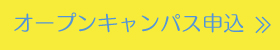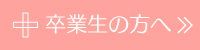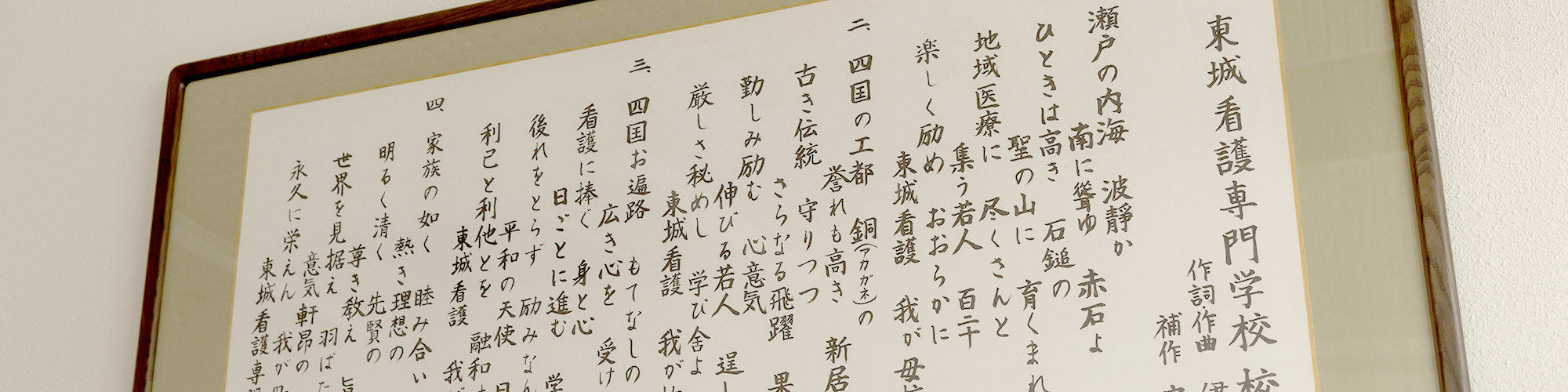
学校評価学校自己点検・自己評価、学校関係者評価
東城看護専門学校は、「2024年度東城看護専門学校 学校自己点検・自己評価報告書」の結果をもとに、学校関係者評価を実施いたしましたので、以下の通り報告いたします。
学校自己点検・自己評価、
学校関係者評価2024年度
2024年度東城看護専門学校
学校自己点検・自己評価結果報告
*横スクロールして確認してください。
| 領域 | 大項目 | 大項目平均点 | 中項目 | 中項目平均点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24年度 | 23年度 | 24年度 | 23年度 | |||
| Ⅰ | 教育理念・教育目的 | 3.8 | 3.7 | 適切な教育理念・教育目的を定める | 3.8 | 3.7 |
| Ⅱ | 教育目標 | 3.7 | 3.7 | 適切な教育目標を定める | 3.7 | 3.7 |
| Ⅲ | 教育課程経営 | 3.5 | 3.5 | ①教育経営者の活動を示す | 3.1 | 2.9 |
| ②適切な科目・単元構成を行う | 3.5 | 3.6 | ||||
| ③適切な教育計画を作成する | 3.5 | 3.7 | ||||
| ④適切な教育過程評価の体系を整える | 3.4 | 3.6 | ||||
| ⑤教員の教育活動の充実をはかる | 3.4 | 3.3 | ||||
| ⑥看護実習体制の保障に努める | 3.7 | 3.5 | ||||
| Ⅳ | 教授・学習・評価過程 | 3.5 | 3.6 | ①授業内容と教育課程との一貫性妥当性を保つ | 3.5 | 3.5 |
| ②適切な授業の展開過程を展開する | 3.5 | 3.8 | ||||
| Ⅴ | 経営・管理過程 | 3.5 | 3.4 | ①目標達成の評価とフィードバックに努める | 3.4 | 3.4 |
| ②学習への動機づけと支援に努める | 3.8 | 3.7 | ||||
| ③東城看護専門学校の意思・指針を示す | 3.6 | 3.6 | ||||
| ④組織体制を整える | 3.6 | 3.5 | ||||
| ⑤財政基盤の周知を図る | 3.2 | 3.0 | ||||
| ⑥施設設備の整備の充実に努める | 3.2 | 3.0 | ||||
| ⑦学生生活の支援を行う | 3.6 | 3.8 | ||||
| ⑧養成所に関する情報提供を行う | 3.7 | 3.7 | ||||
| ⑨運営計画と将来構想を示す | 3.4 | 3.6 | ||||
| ⑩自己点検・自己評価体制の活用を図る | 3.5 | 3.2 | ||||
| Ⅵ | 入学 | 3.3 | 3.3 | 適性のある入学生の確保に努める | 3.3 | 3.4 |
| Ⅶ | 卒業・就業・進学 | 3.2 | 3.2 | 卒業生の状況を把握しその評価を受ける | 3.2 | 3.3 |
| Ⅷ | 地域社会/国際交流 | 3.5 | 3.4 | 地域社会の動向を把握する | 3.5 | 3.5 |
| Ⅸ | 研究 | 3.4 | 2.7 | 教員の研究活動の充実を図る | 3.4 | 2.9 |
【評価 4:非常に当てはまる 3:当てはまる 2:あまり当てはまらない 1:まったく当てはまらない】
【教育理念・教育目的・教育目標】
教育理念・教育目的は保健師助産師看護師学校養成所指定規則に沿った内容であり整合性がある。教育理念・教育目的は、アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーと連動しながら、教育内容に反映している。ディプロマポリシーは、新カリキュラム構築にあたり教育目標を「看護師に求められる実践能力と卒業時の到達目標」に対応させ、卒業後に貢献できる看護師像の指針としている。また、教育理念、教育目的は、学校長の具体的な指針とともに学校パンフレット、学校ホームページなどに明示しており、オープンキャンパス、外部との会議、実習依頼など様々な場面で伝えている。入学式終了後の学校説明会で、入学生と父母等に「学生便覧」を用いて説明している。学生には、入学後のオリエンテーションでも再度説明している。
【教育課程,授業・学習・評価】
教育活動において、令和4(2022)年度から改正カリキュラムは3年目となり完成年度を迎えた。令和6年度は新設科目の講義や実習、新規実習施設での実習を開始し、順調に進めることができた。2年目や3年目の科目についても前年度の評価をもとに、教育内容・方法を工夫し、また専任教員、非常勤講師との連携を図り、順調に進めることができた。また、「看護師教育の技術項目と卒業時の到達度(厚生労働省)」において、排泄の摘便の看護技術が「一人で実施できる」の項目に変更となった為、摘便・浣腸モデルを新規に購入し、教材の充実を図った。
臨地実習は、各実習施設において、運営会議、担当者会議(打合せ会、振り返り会等)を開催し、指導方針や体制を整えている。実習施設に再度の新カリキュラムの内容を伝えて、実習指導の方法などを検討した。
看護師国家試験に向け、1年次後半より対策を立て、2年次より模擬試験や集団指導を実施した。3年次には集団指導に加え、個別指導を実施した。
しかし、令和6年度「第114回看護師国家試験」は、1人不合格で、91.66%の合格率であった。不合格の学生に対して、准看護師として働きながら国試対策ができるように、就職した施設と連携を取りながら援助していくこととした。
次年度は合格率100%を目指し、メンタル面、体調面、学習不足などの支援を、学校全体で討議しながら取り組んでいく。
【経営・管理】
養成所の組織体制は、教育理念・目的を達成するために職務及び服務に関する規程で職務権限や役割機能を明確にしている。学校運営に関わる重要事項は学校運営会議、教務は教務会議、教務以外の事項は職員会議と意思決定システムが明確になっている。教職員の意思が反映できる様に関係する各種委員会に参加して意思決定が出来るシステムを整えている。指定規則で定められている基準を遵守して、適切に学校運営を行っている。
財政基盤を確保の考え方を明確にし、図書費や備品教材費などの予算を確保して、学習・教育の質の維持・向上につなげている。予算計画には、教職員それぞれの観点から要望を確認して、次年度に必要なヒト・モノを確保した上で収支計画を作成している。
管理者は、学習・教育環境の考え方を明示し、その考え方にもとづいて、教育備品や施設設備を計画して実施している。医療・看護の発展や学生層変化に合わせ、タブレット端末でデジタル教科書を使用しWi-Fiが使用できる学内環境としている。授業資料の共有や動画を取り入れた学習に繋げる事ができた。
教員によるアドバイザー制度により学習面や生活面の支援で学習意欲継続を行っている。また、教員間で学生情報を共有し、家族との連絡等により家族と一体となった支援策を行った。
オープンキャンパス・入学時に奨学金などの説明会を開催し、実際に多くの学生が施設の奨学金、専門実践教育訓練給付金支援制度、高等教育の修学支援制度を利用している。
毎年、募集活動計画を策定して、入学生獲得の活動を展開している。パンフレットやホームページも見直しを行い、入学希望者に必要な判断材料を提供している。学生募集活動として、県内の高校を訪問や進学相談会への参加、または、公共機関等へパンフレット設置をお願いしている。そして、年3回オープンキャンパスを開催している。しかし、若年人口の減少や大学全入学時代で看護系大学の増加に加え、医療以外の労働条件の良い仕事に流れている可能性が示唆され、入学者数確保に苦戦している。
【就業・進学】
卒業時の看護師教育の技術項目と卒業時の到達度や就職状況など卒業直後の状況は把握できている。卒業生の本校への訪問などで、一部の施設にいる卒業生の現状を把握が出来ている。一方、連絡のとれない卒業生に関しては、クラスメイト同士など横の繋がりも活用しながら、卒業生の現状課題の把握を努めている。本年度は国家試験不合格者が1名おり、就職先と連携を取りながら、次年度の合格に向けて、就業継続に繋がるようフォロー体制を整えて取り組みをしている。今後は、卒業生の就職先との情報交換や調査の実施等ができる体制を整えていき、卒業生の現状課題の把握を努めて、学内の教育内容、教育方法の検討に活用する必要がある。
【教員の研究活動の充実】
教員の専門分野の研究活動(時間的・財政的・環境的)に関する支援を実施している。研修や学会参加は、出張や代休付与、出張費という形で支援体制をとっている。また、オンライン開催やオンデマンド視聴可能なセミナーが無料で開催されることも多く、教員は勤務時間内でも申告して受講できることとして、教員の自己啓発支援を行っている。
学校として研究活動は行えていない現状である。
学校関係者評価
1.方法
学校関係者評価委員(本校では教育関係者、実習施設看護関係者、卒業生に委嘱)4人が書類による学校関係者評価を行い、各委員の点数の平均を評価点とした。
2.結果
【教育理念・教育目的・教育目標】
建学の精神に立脚した教育理念、教育目標が定められている。その理念、目的を達成すべく教育活動の充実が図られている。
【カリキュラム・教授・学習・評価】
多様な側面から教育目標が相互に関連することで統一性のあるものになっている。教育理念・目的・目標に対応した科目、単元がバランスよく構成されている。学生の学びを支え充実させるための方策が細部にわたって定められている。細部に配慮した充実の実習体制が確立されている。授業内容の段階的理解を促すように教育課程が設定されている。学びの意欲を喚起するために多様な授業形態がバランスよく配置されている。
【経営・管理】
評価活動の多様な機能(対学生・教育活動・目標達成)が互いに連動して、教育活動の質的向上に寄与している。経済的な支援を含め学生の学びを継続的に支える体制が確立されている。多様な媒体を活用して学校情報の提供がなされている。地域に密着した養成校の姿をアピールする機会となっている。自己点検評価活動が教育活動のアップデートを促す機会として定着している学内で開かれる行事や事業が、地域の動向、ニーズを知る良い機会となっている。
2024年学校自己評価(教職員)と学校関係者評価
*横スクロールして確認してください。
| 評価者\項目 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教職員(平均値) | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 |
| 学校関係者(平均値) | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 |
【評価 4:非常に当てはまる 3:当てはまる 2:あまり当てはまらない 1:まったく当てはまらない】